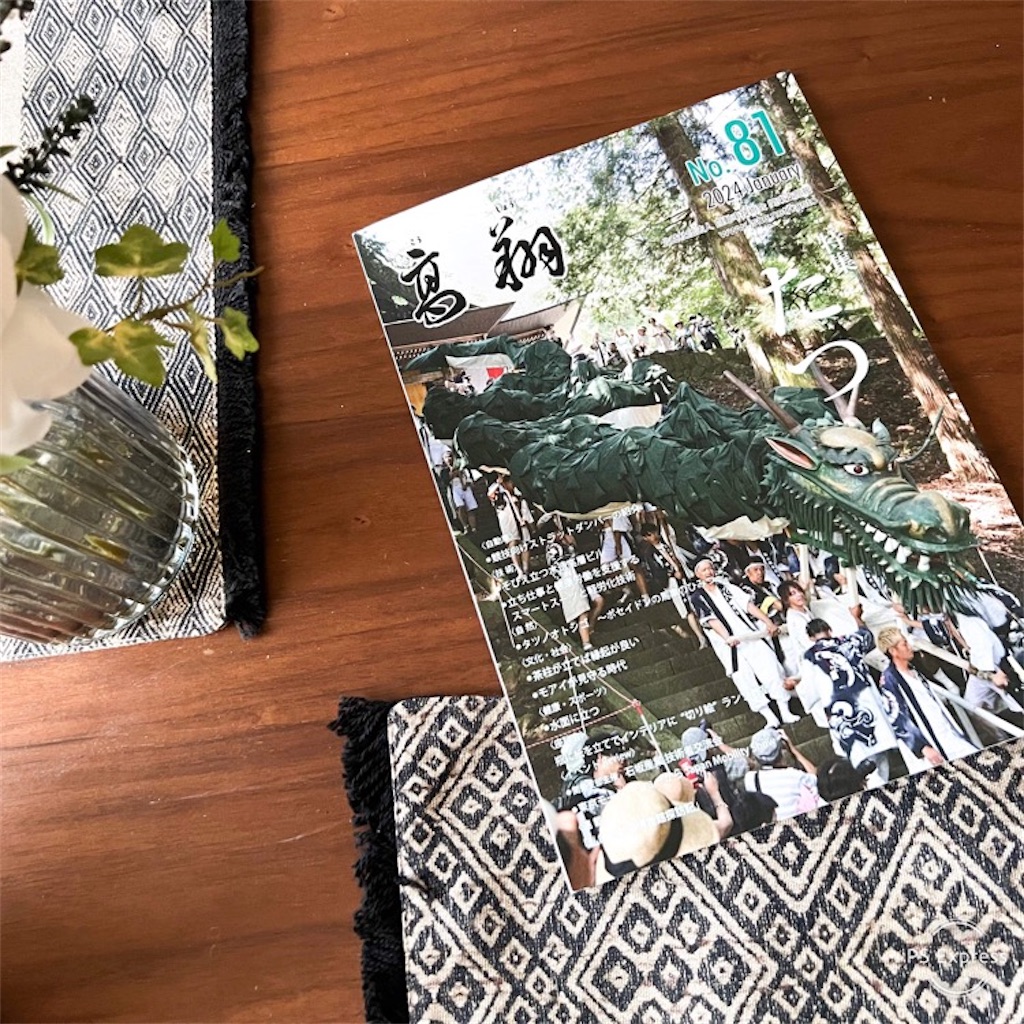桜の展覧会、無事終了いたしました!
桜の淡さは、他のどこの国にもない、儚くも美しい風景。その景色を鑑賞する習慣は、平安時代から始まったとされています。弥生時代には、桜は穀物の神が宿る樹木として祀られていました。毎年春にこの桜の美しい世界を経験する日本人の遺伝子には、その美しさが深く刻み込まれています。日本人が、世界中が愛する桜の景色がそれぞれの作家の感じるままに描かれ、このGallery Aoyama Iyasakaに集結いたしました。


ギャラリーでは、今回の期間に向けて開花された桜を見ながら茶人にお抹茶を立てて頂き、桜餅のセットをお楽しみいただくことが出来、作家さんたちの桜作品の力作により、日本文化の良いところをたくさん凝縮して体感いただける最高の空間となりました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました!
以下に、各作家さんたちの今回の桜作品についてのご紹介をさせて頂きます。

◆ひら子/切り絵
『「願わくは 花の下にて 春死なん その如月の 望月の頃 西行 散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ 細川ガラシャ」平安時代から何度目の春でしょうか。 幾度となく歌に詠まれ、たくさんの人が桜を眺めて心を震わせてきたでしょう。満開の桜だけでなく、散り際の潔さに諸行無常、どことなく切ない気持ちになります。 桜の作品を作りたいと思ったのは上京して最初の春のことでした。
記憶の中の夜桜は相変わらず美しい。ただ悠然と存在する姿は美しいだけではない、何か禍々しい魔性のようです。 あの日見た夜桜にどれほど近づくことができたでしょうか。とても大変な制作でしたが、それでもあの夜桜はまだ遠い。 けれどまたいつか作りたいと思います。 平安時代の始まりから1230回目の春に、こうして桜を題材にした作品を作ることができて光栄に思います。 素晴らしい機会をいただきましてありがとうございます。』

◆荻原久代/油絵
『桜咲く、桜散る、などの桜言葉を3月下旬〜4月上旬に味わえるのは東京の醍醐味だと思う。数多くの歌や文学などが東京で生まれているのがよくわかる。 昔、チシマザクラという山桜を見るために山登りをしたのを思い出す。確か5月〜6月あたり。桜を見るために大変な思いをしたのと、卒業入学シーズンでもない時に桜を見るという、世間から離れた独特の時差が当時は面白かった。今回の「揺らぎ」という桜の絵を描いたが、やはり昔と今の思いが重なって、桜に思いを乗せる形となった。ピンク色に揺れる桜を見ると日本に生まれてよかったと思える。 私の創作活動の源にはいつも育ててくれた島の思い出がある。』

◆樫内あずみ/アクリル
『真っ黒な幹の中にピンクが渦巻き、春になると、花としてそれをハラハラと爆発させる。 「桜の魅力、それは木の幹」だと、小さい頃から思っていました。あの黒が大好きです。 今回、作品「やまのこえ」を制作しながら、桜に思いをはせてみました。 描きながら、桜というものは、日本社会の中でも独特な立ち位置にいるのだなと改めて感じました。桜のどくどくした生命力と、はじける開放感は、春を感じます。』
私の普段の活動としては、手で直接触れることのできる「触れる絵画」と、即興でたった一人のために絵を描く「絵詠み」をメインに行なっています。 活動を通して一人ひとりにとっての「人生の宝物」を見つめる機会を提供し、自分の手で自分の人生を豊かにする人が増える事を願っています。

◆タンタン/切り絵
『水辺に輝く、桜の幻。桜は淡く短命。本当にそこにあったのかさえわからない。水面に反射している桜が幻なのか、それともリアルなのか。少しでも刺激が加われば、波紋とともに、瞬く間にかき消されるその景色。桜は、この水面に反射した桜と同じ。それでも毎年桜は咲き、美しく散る。その有様は、人の世そのもの。そんな情景を「反射」に描きました。そして、この作品で用いた切り絵をもとに、切り絵版画という新しい手法で、ぼんやりと黒く浮かび上がる桜に、淡く燃える短命な桜の瞬きを、火の粉の輝きで「燃ゆる桜」に映し出しました。』
それぞれに力強い作品が展開されました。
私とは正反対の切り絵を作るひら子さんは、この桜は3部作のうちの1つだそうです。3つそろったら圧巻だろうな。私自身は、モノクロの切り絵が苦手なんだけど、ひら子さんの切り絵はなぜか胸にスッと入る。なんて話を繰り広げていました。
なんでだろうと思っていたら、会場にいらしたするどい人が、モノクロで黒の部分が多いけど、雰囲気が明るいからじゃないかな?と。なるほど。そのするどい人は、私が今回の作品あたりからやっと芸術にまで昇華出来始めたことも言い当てました。これまでの私の作品は、綺麗だけどどちらかというとインテリアアート。
インテリアアートも良いけれど、やっぱり心の深いところに届けたいとなると、何か物足りない。そんな物足りなかった部分が、少し、今回の桜の展覧会で見えてきた感じがしました。
日頃から真剣に作品に向き合い、力強い作品を生み出している作家さんたちとの出会いのおかげです。
桜の開花はこれから。
淡いピンクの世界で町中が幸せになりますように。